【思ったこと】170310(金)オドノヒュー&ファーガソン『スキナーの心理学』(22)第4章 徹底的行動主義(4)
3月9日の続き。
第4章では続いて、科学とは何かについてのスキナーの考えが紹介されている。【長谷川による要約・改変】
- 【スキナーは】自然界の法則を明らかにするには実験が必要だと主張している。これが彼自身の科学を実験行動分析と称した理由である。実験では、他の変数を一定に保ち、1変数(独立変数)のみを操作する。したがって、実験によって、観察される従属変数の変化をもたらした原因が独立変数のせいだということが明らかになる。従属変数(その値が独立変数の値に依存するので従属という)こそが、われわれが求める予測と統制の変数である。
- スキナーにとって、原因結果関係とは、関数式で表現できるということである。独立変数は、普通、グラフではx軸になり、従属変数はy軸になる。たとえば、強化量(独立変数)を操作し、行動の生起頻度(従属変数)の変化をグラフに描き、関数関係が見られたら、それが原因結果関係なのである。
- 重要なのは原因の発見である。それがわかれば、現象の予測と統制が可能になる。スキナーは、科学の実際上の目的は予測と統制だと考えた。予測ができれば、特定事態でどんなことが生ずるのか、その知識を高め、適切な準備が可能になる。統制ができれば、目標に合わせて状況を準備することが可能になる。科学的実験は、この目的を達成するための方法なのである。
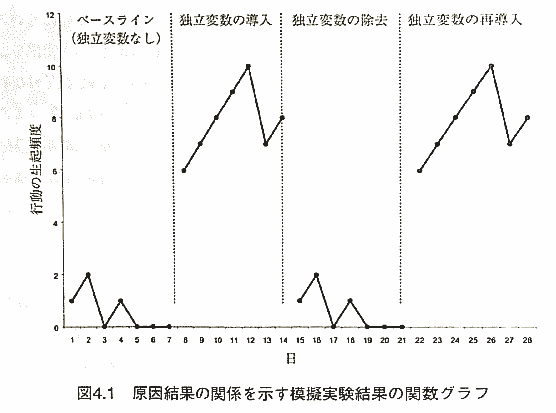 上記では関数式で表現できることの重要性が強調されているが、この部分についても若干の疑義がある。というのは、本書の説明文で「原因結果の関係を示す模擬実験結果の関数グラフ」として掲載されているのは、実際には、独立変数を横軸とした従属変数のグラフではない。横軸は、日にちの経過であって、描かれているのは、ベースライン条件と実験条件における生起頻度を折れ線グラフにしただけである。
上記では関数式で表現できることの重要性が強調されているが、この部分についても若干の疑義がある。というのは、本書の説明文で「原因結果の関係を示す模擬実験結果の関数グラフ」として掲載されているのは、実際には、独立変数を横軸とした従属変数のグラフではない。横軸は、日にちの経過であって、描かれているのは、ベースライン条件と実験条件における生起頻度を折れ線グラフにしただけである。
もっとも、元の英語版では、図のタイトルは「An experiment demonstrating a functional-causal relationship.」、直訳すれば「機能的因果関係を示す実験例」であって、「関数グラフ」という言葉はどこにもない。いずれにせよ、関数グラフの例として左図を挙げるのは誤解を招くように思う。
また、2月26日の日記で述べたように、「functional relationships」と言っても、量的に精緻化された「関数関係」というよりも、行動と、それに増減に影響を及ぼす環境変数との質的な「機能的関係」を明確にすることを研究の目的とすべきであると私は考えている。リンク先を再掲すると、「関数関係」といっても、せいぜい、
- 複数の要因が影響を及ぼしている場合、それらは独立しているか、相互作用として影響しているのか。
- 複数の要因の影響の大きさは、どちらが優位か。
- どの範囲で影響を及ぼすのか。
- 単調な増加(現象)をもたらすか。山型(上に凸)か谷型(下に凸)のような関係か。
程度が判明すればよい。それ以上の細かい量的関係は、殆ど無意味であり、じっさい、一般式を持ち込んでも、個体差が大きすぎて意味をなさないように思う。
なお、左の図は一事例の実験デザイン、いわゆるABABデザインであるが、この方法が、予測と制御(もしくは影響)に万能であるかどうかについても若干疑義がある。というのは、独立変数の種類や影響も、行動変容に伴って変化していくからである。例えば、子どもにピアノのお稽古を身につけさせようとした時、
- A1:最初のベースラインでは、子どもに好き勝手に練習させる。
- B1:次の実験条件では、30分のお稽古をするたびに、ご褒美を与える。
という条件を設定するとB1では、お稽古という行動が増大する(強化される)はずである。ここで、次に、第2ベースライン期(A2)を導入することになるが、B1でピアノを上手に弾けるようになった子どもであれば、もはや、ご褒美など貰えなくても、「ピアノを弾く→美しいメロディ」という自然随伴性によって、自走型のお稽古を続けられるようになるかもしれない。そうなれば、もはや、第2実験条件も不要となる。
もう1つ、こうした単一事例の実験デザインは、普遍的な因果関係を証明する手段としては甚だこころもとない。というより、この方法は、機能的文脈主義であればこそ有用なデザインとなる。バッハ・モラン(2009、54〜55頁)は、この点に関して次のように述べている。
分析のユニット
機能的文脈主義(functionalcontextualism)は,分析の対象として,現在進行中の文脈の中での行為(ongoingact-in-context)に焦点を当てる(対象を部品からなる機械のように捉えるのとは異なる)。機能的文脈主義の分析は,現在,生じているクライエントのふるまいと,そのふるまいが生じる環境を重視する。分析の対象となるものは,相互に関連したユニットである。したがって,4項随伴性の動因操作,弁別刺激,反応,結果刺激についても,実際にはそれらは単一のユニットなのである。つまり,分析の対象となるのは,4つの異なった部分というより,むしろ1つのまとまりある事象である。
真理基準
機能的文脈主義では,あることが「真である」と言われるのは,それが「ゴールの達成に効果的な実践(successfulworking)」を導くときである。機能的文脈主義に依拠する科学者は,自己の言説がモデルと一致するのか否かを見ることは少なく,それよりも,その言説が望まれる結果をもたらすかどうかに関心を寄せる。そのため,行動分析学の科学者にとって一事例のデザインはより魅力的になるわけである。一事例のデザインとは,ベースラインを測定し,次にその変化を見るため,ある変数を変更する。その後,もう一度,変更した変数を元の状態に戻して,測定対象の指標がベースラインのレベルに戻るかどうかを見るというものである。科学者が「自分の行った介入は,指標を望ましい方向にうまく変化させるであろうか?」という質問に答えるには,帰納的な(一事例のA-B-Aデザイン)研究の方が,演繹的な(仮説検証の)研究よりも適しているのである。
バッハ・モラン(著)武藤崇・吉岡昌子・石川健介・熊野宏昭(監訳)(2009).ACT(ア クセプタンス&コミットメント・セラピー)を実践する. 星和書店.【Bach, P.A., & Moran, D. J. (2008). ACT in practice Case conceptualization in Acceptance & Commitment Therapy. Oakland, CA: New Harbinger Publicarions.】
次回に続く。
|


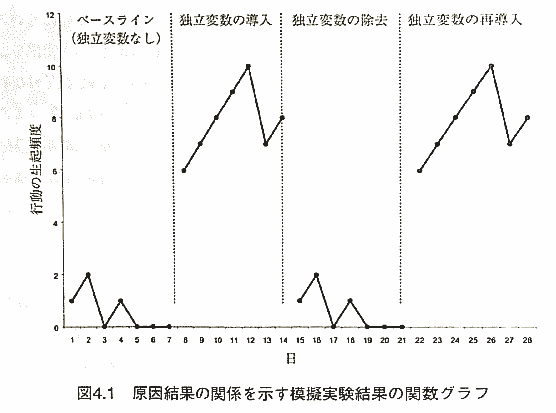 上記では関数式で表現できることの重要性が強調されているが、この部分についても若干の疑義がある。というのは、本書の説明文で「原因結果の関係を示す模擬実験結果の関数グラフ」として掲載されているのは、実際には、独立変数を横軸とした従属変数のグラフではない。横軸は、日にちの経過であって、描かれているのは、ベースライン条件と実験条件における生起頻度を折れ線グラフにしただけである。
上記では関数式で表現できることの重要性が強調されているが、この部分についても若干の疑義がある。というのは、本書の説明文で「原因結果の関係を示す模擬実験結果の関数グラフ」として掲載されているのは、実際には、独立変数を横軸とした従属変数のグラフではない。横軸は、日にちの経過であって、描かれているのは、ベースライン条件と実験条件における生起頻度を折れ線グラフにしただけである。